令和7年度(第32回)

| 選考 |
令和7年9月9日(火曜日)に第32回丸山薫賞の選考が行われ、眞神 博(まがみ ひろし)さんの詩集『精神の配達』(風詠社刊)に決定しました。
|
|
選
考
経
過
と受賞理由
|
(選考委員 細見和之 記)
第32回丸山薫賞の選考は本年9月9日(火)、豊橋市役所内で行われた。当初は9月5日(金)に実施の予定であったのが、台風の影響で延期されたものである。
選考委員は高階杞一、高橋順子、中本道代、細見和之、八木幹夫の5名。
全国から応募のあった詩集、推薦された詩集を合わせた選考対象詩集の中から、選考委員がそれぞれ2冊以内を選び候補詩集とした。
候補詩集として挙げられたのは以下の9冊だった(並びは書名の50音順)
十田撓子『あさつなぎ』(Le Petit Nomade)
服部 誕『失せもんめっけもん』(編集工房ノア)
柴田康弘『しがらみの街』(書誌侃侃房)
眞神 博『精神の配達』(風詠社)
田村雅之『魂匣』(砂子屋書房)
廿楽順治『鉄塔王国の恐怖』(改行屋書店)
和田まさ子『途中の話』(思潮社)
リクター香子『冬の孔雀』(花梨社)
照井知二『養年』(土曜美術社出版販売)
まず各委員が順に自分が推す詩集についての推薦理由を述べた。
『あさつなぎ』は秋田の風土性を色濃く纏い、氷や雪に閉ざされた表面からは見えにくい人間のドラマ、動物の命などに目を凝らして繊細な言葉で綴っている。秘められているドラマは断片的だが、作者の緻密な筆づかいには、そのドラマを読み手に想像させる力がある。
『失せもんめっけもん』は昭和の風物をなぞりながら、そこに言葉遊びの要素も交えている、実質的には言葉がテーマの詩集。よくこれだけの言葉を収集したと感嘆する。すべての作品をソネット形式に収めている手腕も鮮やかである。
『しがらみの街』は、春から冬へと季節の順に作品が配列され、移りゆく季節に日々の思いが重ねられている。どの作品にも透明感があり、静謐な言葉の隙間から生きていることの痛みも伝わってくる。
『精神の配達』は、キリスト教の世界観が背景にあると思われるが、通常の言葉の運び方を脱臼させて、この世界のロジックとは違うものを一所懸命に探している。この世界に投げ出されている受動性と徹底的に向き合い、その先を手探りする貴重な言葉の実験が光る。さながらカフカが詩を書けばこうではなかったかと思わせられる。
『魂匣』は日本語の古語へのこだわりを、アイヌ語までを引き込みながら、独特の形で追求している。詩人の奥底に眠っている日本語への一種の遡及感、日本語への憧れのようなものを体現した詩集。
『鉄塔王国の恐怖』は、版画と詩が絶妙に絡み合い、奇抜な世界が広がっている。行間に飛躍があって、どこへ向かうのか分からない、ドキドキするおもしろさに満ちている。軽薄や低俗を装いながら、そのうちには権威や倫理に対する痛烈な批判が込められている。
『途中の話』は、東京の風景と文学者の事績を結びつける作品をはじめ、日常的な発見が巧みな構成をもった詩として展開され、ときに強い言葉も放たれている。全部を言ってしまわずに終わらせる、空白の見つけ方も優れている。
『冬の孔雀』は、海外で暮らしている作者が生活の細部を瑞々しく捉えている。ほとんどが『抒情文芸』に投稿して発表された作品だが、1編の中に必ずきらめく一行がある。生のままの感性が生かされている清々しい作品世界である。
『養年』は、裏通りの人生、陽の当たらない人生を生きている人たちに対する哀惜の念、彼らの人生を救い上げたいという願いによって書かれた詩集。前詩集ではすべて短詩で描いていた作者がここでは息の長い作品をつうじて、夢の養い、希望の養いをテーマとしている貴重な詩集である。
以上のような推薦理由が述べられたあと、1冊ずつについて各委員が意見を述べ、自由に意見を交わし合った。その後、それぞれ一人が3冊を選ぶことになり、『あさつなぎ』『精神の配達』『途中の話』が上位3冊として残った。この3冊についてさらに議論が重ねられた。
『あさつなぎ』については、前半の作品が優れている一方で、後半に修辞上疑問を感じる箇所、あえて刺激的な表現で衝撃を与えようとしている箇所が散見する、という指摘があった。
『精神の配達』については、作者によってのみ可能な言葉の新鮮な捉え方を評価する一方、作品の難解さを指摘して、丸山薫賞にふさわしいのか、という意見も出された。
『途中の話』については、優れた詩集として評価しつつも、すでに小野十三郎賞を授与されていることに鑑みて別の作品に光をあてるべきではないか、という意見があった。
こうした議論のなか、なかなか全員一致で1冊に絞ることができなかったが、相互の批評をつうじて『精神の配達』を4人の委員が推すことになり、『精神の配達』を授賞作とすることに決定した。『精神の配達』は、作者独自の言葉の感触とその配列をつうじた、ほかには見られない精神世界を手探りする詩集であることが高く評価された。
(文中敬称略)
|
| 受賞者紹介 |
1950年東京生まれ。明治大学付属高等学校卒業後、ゲーテ・インスティテュート東京にてドイツ語を学び、出版社、印刷会社勤務を経て現在は文筆活動に専念。
1968年詩誌「秘夢」創刊に参加、1973年から1977年まで詩・美術雑誌「おらんぴあ」発行、2003年から2013年まで詩誌「現代詩図鑑」発行、現在詩誌「ユルトラ・バルズ」同人、日本現代詩人会所属。既刊詩集に、「ひかるかー透明な音楽」1969年、「嬉遊曲」1970年、「舗装」1996年、「焼きつくすささげもの」2001年、「修室」2008年。「精神の配達」は第六詩集。
|

眞神 博 さん
|
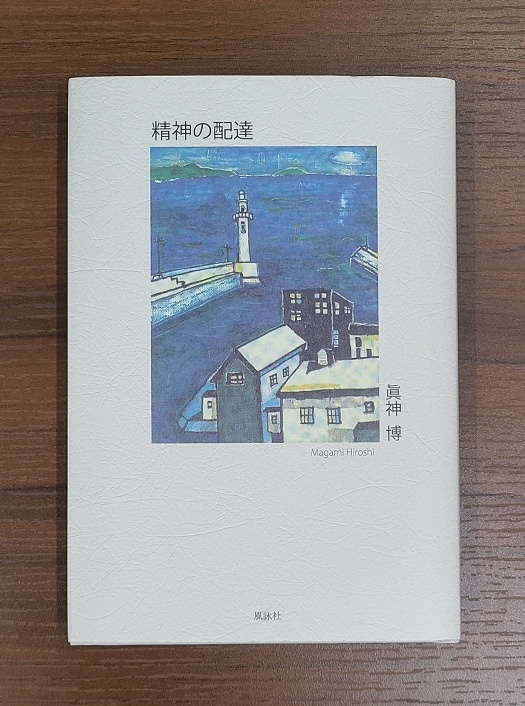
「精神の配達」
|
| 受賞の感想 |
このたびはいつも遠くから眺めておりました栄えある賞をいただき感慨無量です。これまで取り囲まれた現実の戸を叩くようにして詩を書き、詩集をまとめてきましたが、その扉が突然開かれたような驚きと喜びが綯い交ぜになっています。これはあらたな局面での詩作への促しであるとも受け止めています。近代詩から現代詩への流れの中で、ともすれば野放図になりがちな言葉を律する力をもち、多くの人から親しまれ崇敬の念を抱かれている詩人丸山 薫の作品は、これからもつねに立ち返るべき道標でありつづけるでしょう。受賞にあたり選考委員の皆様、豊橋市文化課の皆様に心から御礼を申し上げます。
|
| 贈呈式 |
令和7年10月21日(火曜日)、豊橋市内のホテルで贈呈式が行われました。

|